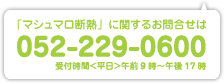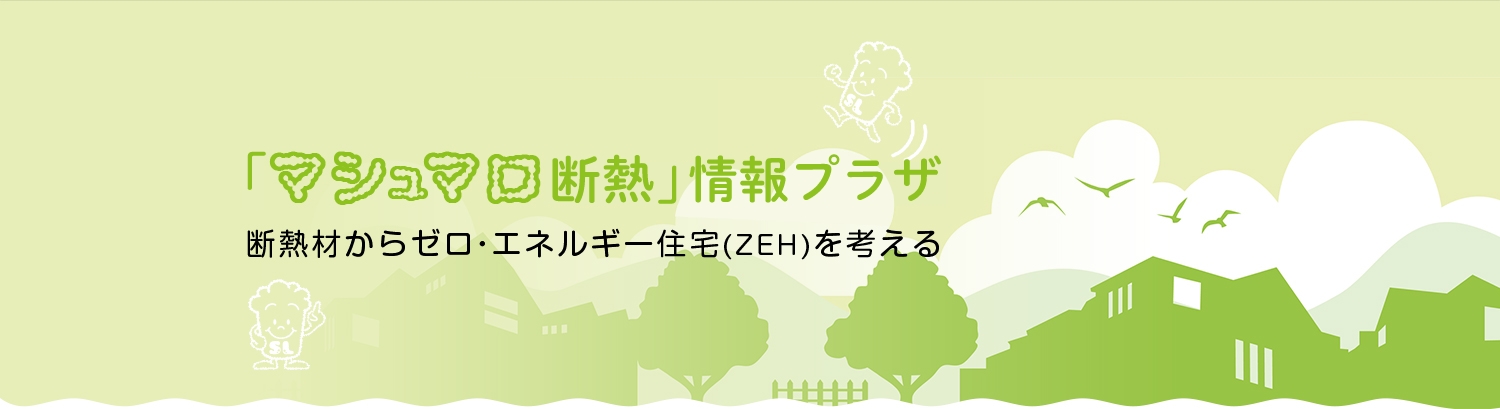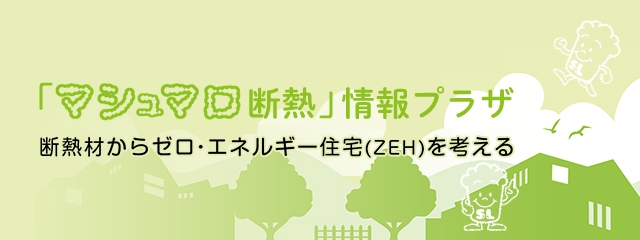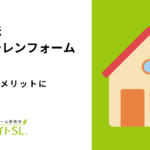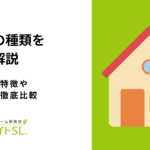目次

断熱材には多数の種類があり、何を基準に選べば良いかわからない方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな時、断熱材を選ぶ基準として活用できるのが熱伝導率や熱抵抗値といった数値です。
今回の記事では、断熱材の熱伝導率とは何か、熱抵抗値との違いや計算方法をご紹介します。
▼この記事でわかる内容
- 断熱材の熱伝導率とは
- 熱伝導率と熱抵抗値の違い
- 熱伝導率・熱抵抗値の計算方法
- 各断熱材の熱伝導率・熱抵抗値・厚さを一覧で解説
- 断熱材選びで気をつけたいポイント
各断熱材の数値比較も行いますので、断熱材選びで迷っている方は参考にしてみてください。
フォームライトSLは、現場発泡させる吹き付けウレタンフォームです。壁の中を隙間なく断熱材で充填できるため、隙間ができず快適な居住空間を作り出すことができます。
フォームライトSLの特徴は以下の通りです。
- 優れたコストパフォーマンス
- ランニングコストが経済的
- 断熱工事と気密工事を同時対応できるため工期はおよそ2日間
断熱材選びに迷われている方は、ぜひ詳細が記載されたカタログをダウンロードしてみてください。
断熱材の熱伝導率とは

断熱材の熱伝導率とは、その断熱材が熱をどれだけ伝えやすいかを表す数値です。
熱伝導率が低いほど、熱を伝えにくく、断熱性能が高いということになります。イメージとしては、熱の伝わりやすさを表す「早さ」のようなものです。
例えば、以下のように表現することができます。
- 熱伝導率が高い=熱が速く伝わる=断熱性能が低い
- 熱伝導率が低い=熱がゆっくり伝わる=断熱性能が高い
熱伝導率は、W/(m・K)という単位で表されます。これは、1mの厚さの材料の両端に1℃の温度差がある時、1秒間にどれだけの熱量が流れるかを示しています。
熱伝導率と熱抵抗値の違い
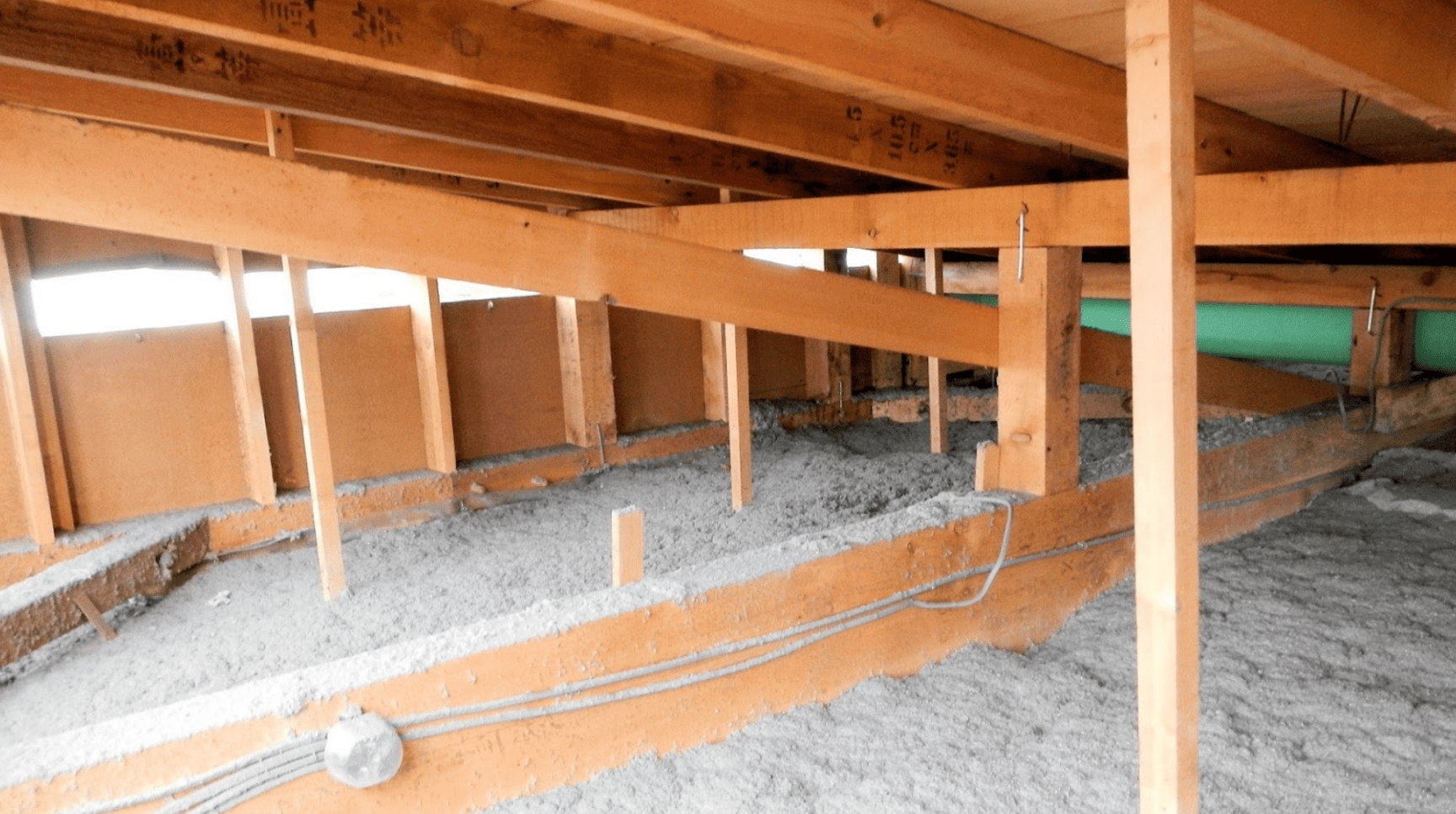
熱伝導率と熱抵抗値は、どちらも材料の熱の伝わりやすさを示す指標ですが、視点が異なります。
熱伝導率は、材料そのものの熱の伝わりやすさを表します。値が小さいほど熱を伝えにくく、断熱性能が高いことを示します。単位はW/(m・K)で、材料の厚さは考慮しません。
一方、熱抵抗値は、材料の厚さを考慮した熱の伝わりにくさを表します。値が大きいほど熱を伝えにくく、断熱性能が高いことを示します。単位は㎡・K/Wです。
例えるなら、熱伝導率は水道の蛇口の太さ、熱抵抗値は蛇口に付けたフィルターのようなものです。太い蛇口ほど水がたくさん流れ、厚いフィルターほど水の勢いは弱まります。
|
項目 |
熱伝導率 |
熱抵抗値 |
|
熱の伝わりやすさ |
伝わりやすい |
伝わりにくい |
|
値 |
小さいほど熱を伝えにくい |
大きいほど熱を伝えにくい |
|
単位 |
W/(m・K) |
㎡・K/W |
|
厚さ |
考慮しない |
考慮する |
|
説明 |
材料そのものの熱の伝わりやすさ |
材料の厚さを考慮した熱の伝わりにくさ |
熱伝導率・熱抵抗値の計算方法
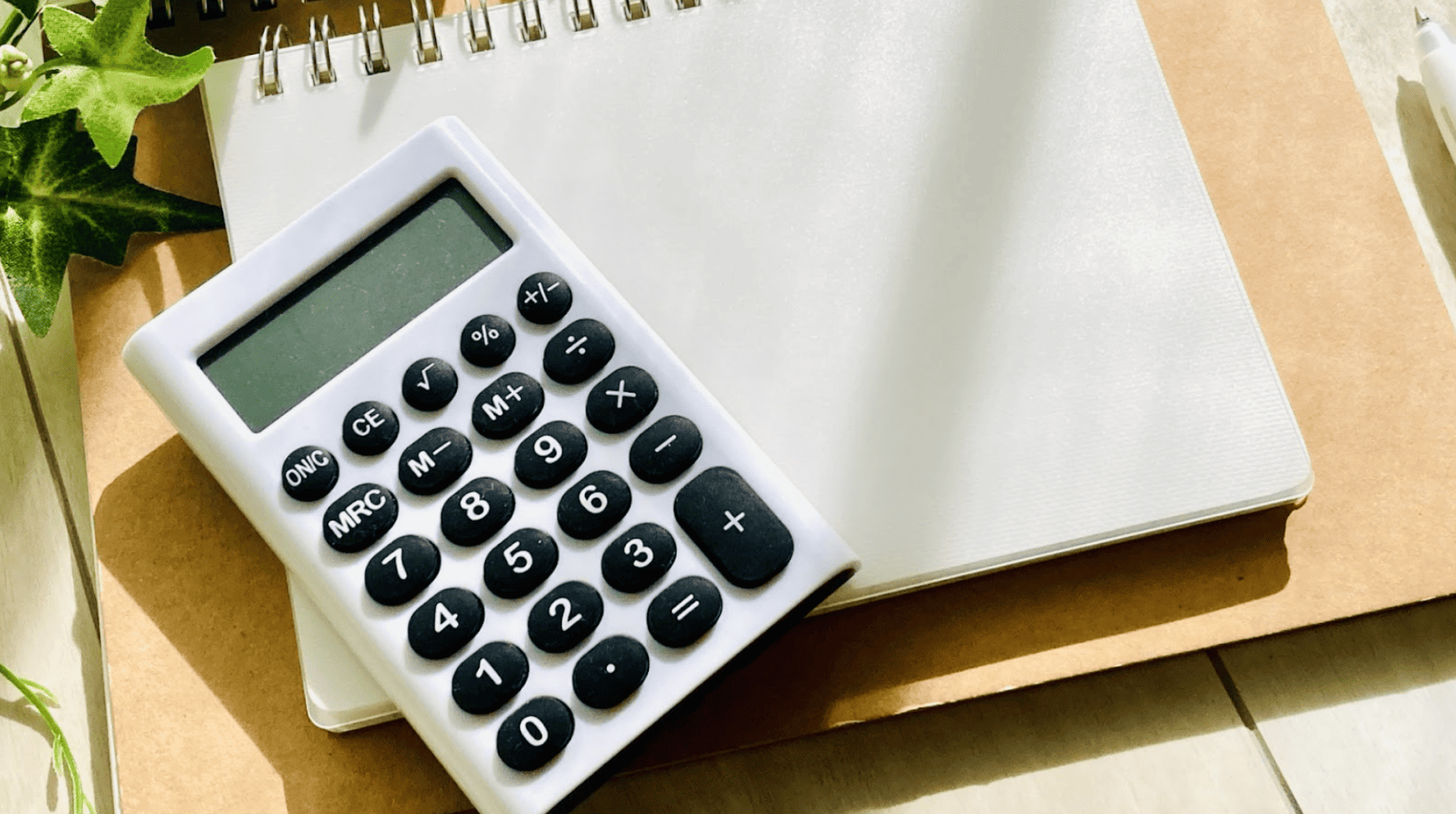
熱伝導率・熱抵抗値は以下の計算式で求めることができます。
|
熱抵抗値(m2・K/w)=断熱材の厚み(m)÷断熱材の熱伝導率(w/m・K) |
例えば、厚さ100mm(0.1m)、熱伝導率0.040W/m・Kの断熱材の場合、熱抵抗値は0.1m÷0.040W/m・K=2.5m²・K/Wです。
各断熱材の熱伝導率・熱抵抗値・厚さを一覧で解説

ここからは、代表的な断熱材の熱伝導率・熱抵抗値・厚さを一覧で解説します。
|
ウレタンフォーム |
グラスウール |
|
|
熱伝導率 |
0.040W/m・K以下、0.026W/m・K以下 |
0.032 W/m・K(高性能36K品)~0.050 W/m・K(10K品) |
|
経年変化 |
・ウレタンフォームの密度は軽量に設計しており、木材の痩せや膨張にも追従できるように接着性も強化しており、断熱欠損が生じ難く、経年変化も起きにくい。 繊維系断熱材のような垂れ下がりは起きないため、気密性・断熱性の低下は起きにくい。 また、断熱層が空気で形成されているので、層内の空気が外部の空気と置換できるので断熱性能は維持されます。
|
・施工精度によって初期の気密性や断熱性が大きく左右されるため、経年劣化の早さや大きさも左右されてしまう。 ・高性能化が進むにつれ、密度が重くなっているため、自重による垂れ下がりが懸念される。 ・繊維内部への湿気の浸入によって、断熱性能の劣化が起きやすい。 |
断熱材①|ウレタンフォーム
吹付硬質ウレタンフォームは、ポリウレタン樹脂を発泡させてつくる断熱材です。
硬質ウレタンフォームは小さな硬い泡の集合体でできており、熱を伝えにくい性質を持つため、高い断熱性能を有しています。気密性が高く、隙間なく施工できるため、高い断熱性能を発揮します。
また、ウレタンフォームの密度は26kg/㎥と軽量で、木材の痩せや膨張に追従し、接着性を強化することで断熱欠損が生じにくく、経年変化も起きにくいです。
また、透湿抵抗値が高く、湿気を含まないため、繊維系断熱材のような垂れ下がりが起きないため、気密性・断熱性の低下は起きにくいです。さらに、フォーム内部が独立気泡構造のため、外部からの空気の置換が起きにくいです。
|
熱伝導率 |
0.040 W/m・K 以下、0.026 W/m・K 以下 |
断熱材②|グラスウール
グラスウールは、多くの木造住宅で使われているガラス繊維を綿状にした断熱材です。ガラスを高温で溶かし、髪の毛よりも細い繊維状にしたものが綿状に集まったものです。
グラスウールのような繊維系断熱材は、繊維内部への湿気の浸入によって断熱性能が劣化しやすいため、湿気対策として気密フィルムで包まれています。しかし、施工時にタッカーなどで留める際に、この気密フィルムが損傷し、湿気の浸入を許してしまうことがあります。
また、施工精度によって初期の気密性や断熱性が大きく左右されるため、経年劣化の早さや大きさも変わってきます。加えて、高性能化に伴い密度が高くなっているため、自重による垂れ下がりが懸念されます。
湿気の浸入と自重により断熱材が垂れ下がると、熱橋(熱の通り道)が発生し、内部結露の大きな要因となります。さらに、熱橋は断熱欠損にも繋がるため、断熱性も大きく低下させてしまいます。
|
熱伝導率 |
0.032 W/m・K(高性能36K品) ~0.050 W/m・K(10K品) |
断熱材選びで気をつけたいポイント

快適な居住空間を実現するためには、断熱材の存在が不可欠であるため、断熱材選びは慎重に行わなくてはなりません。ここからは、断熱材選びで気をつけたいポイントを3つご紹介します。
▼断熱材選びで気をつけたいポイント
- ポイント①|断熱等級が高いものを選ぶ
- ポイント②|施工箇所に合わせて断熱材を選ぶ
- ポイント③|技術力を持った業者に相談する
ポイント①|断熱等級が高いものを選ぶ
断熱等級とは、住宅の断熱性能を評価する指標です。等級1〜7まであり、数字が大きいほど断熱性能が高いことを示します。
2025年4月から開始する省エネ基準義務化により、住宅の省エネ性能に関する基準が大幅に引き上げられ、これまでの最高等級であった等級4が最低等級として位置付けられることになりました。
また、2030年からは等級5が最低等級になると言われているため、なるべく高い等級の断熱材を使用しておくことが重要です。
断熱等級については以下の記事でも紹介しておりますので参考にしてみてください。
▼関連記事
断熱等級4が最低基準に|2025年4月施工の省エネ義務化の仕様基準を解説。
ポイント②|施工箇所に合わせて断熱材を選ぶ
断熱材は、施工箇所によって適した種類が異なります。それぞれの箇所に適した断熱材を選ぶことで、より効果的に断熱性能を高めることが可能です。
断熱材を選ぶ際には、施工箇所の環境条件も考慮する必要があります。例えば、湿気の多い場所には、防湿性に優れた断熱材を選びましょう。
ポイント③|正しい知識を持った工務店に相談する
断熱材の性能を最大限に引き出すためには、正しい施工が不可欠です。施工は専門的な知識や技術が必要となるため、正しい知識を持った工務店に依頼しましょう。
吹付け断熱の場合は、高い施工力が必要なため、実績や評判などを比較検討することをお勧めします。
断熱材を選ぶなら「フォームライトSL」がおすすめ
フォームライトSLは、現場発泡させるウレタンフォームです。壁の中を隙間なく断熱材で充填できるため、隙間ができず快適な居住空間を作り出すことができます。
断熱等級の最高水準である7等級に対応しており、省エネ性・耐久性・静音性に優れた住宅を実現することが可能です。
また、フォームライトSLの施工は、高い技術を有したマイスター認定施工店が対応するため、安心できる点も魅力的なポイントと言えます。断熱工事と気密工事を同時対応でき、工期はおよそ2日間と短いことも魅力です。
断熱材選びに迷われている方は、ぜひ詳細が記載されたカタログをダウンロードしてみてください。
まとめ

今回の記事では、断熱材の熱伝導率とは何か、熱抵抗値との違いや計算方法をご紹介しました。
熱伝導率とは熱の伝わりやすさを表す数値であり、熱抵抗値とは材料の厚さを考慮した熱の伝わりにくさを表す数値です。
今回の記事でご紹介したように、代表的な断熱材であっても熱伝導率や熱抵抗値はそれぞれに違いがあります。
断熱材選びに迷ったら、熱伝導率や熱抵抗値を1つの指標として確認してみても良いかもしれません。